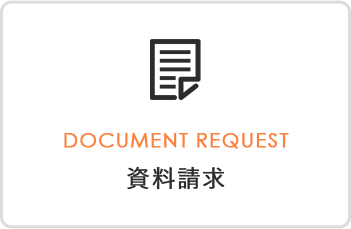ゲスト対談・特集記事
連載
庄内から世界に向けた商品を ~ 玄米デカフェのブランドマネージャー募集にあたって~
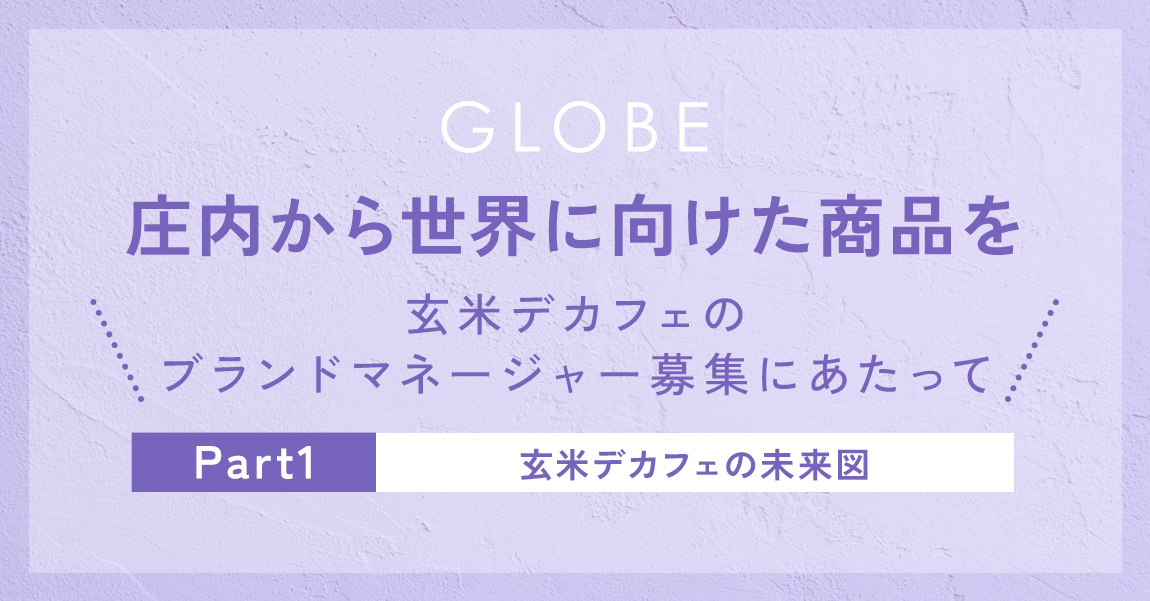
———玄米デカフェは、2012年に開発以来、私たちが大切に育ててきた商品です。
製品群の1つではあるものの、私たちの取り組みの集大成になり得る商品だと思っています。
玄米デカフェを通じて、成し遂げたいビジョンをご理解いただき、
ぜひ想いを共有できる方と一緒に仕事をしたいと願っています。(小澤尚弘)———
Part.1 玄米デカフェの未来図
社長になって以来「これだ」と思ったことは、どんどん行動してきた。
加えて興味の幅が広く、関心も移ろいやすい性格のため、
MNHの事業や商品は「一貫性がない」と映ることもあるようだ。
そんな私にも、ばらばらに手掛けてきたことが1つになる時———
パズルのピースたちが「パチン!」とはまるような瞬間がある。
それが「玄米デカフェ」の今だ。
*
さかのぼること10数年。
MNHは山形・庄内町で事業を進めていた。
地元の食材を使って新しい産品を作るというミッションの中、「お米」を主役にした製品を模索していたのだ。
そこでふと「飲みものにできるかもしれない」と思い付き、自宅のキッチンで玄米を炒ってみた。
2014年の、暑い夏の日の夜だったと思う。
その日以来、何度も実験をかさね、知り合いの珈琲屋のマスターに教えをこいながら、ようやく焙煎らしきことができるようになった。
そのレシピをもとに、山形・庄内町にある工房(*1)でスタッフと量産化を試み、「玄米コーヒー」を売り出していった。
鳴かず飛ばずの時期が続き、業績が悪化するたびに事業をやめる話が持ち上がった。
だが、そのたびに踏ん張って続けてきた。
「お米離れが著しい日本において、経営がひっ迫する米農家を守るため、新しいお米の価値をつくりたい」という初心があったからだ。
「玄米デカフェ」と改名し、リブランディングし始めた、2020年夏。
阪急うめだの本店から声がかかり、初めてポップアップ店舗を出した。
その頃は、“玄米で作ったコーヒー”というだけで、好奇の目にさらされることも多かった。
しかしながら、時代は大きく様変わりした。
温暖化による気候変動は、コーヒーの生産においても深刻な影を落としている。
このまま気候変動が進むと、2050年にはアラビカ種のコーヒー栽培適地は50%にまで減少し、コーヒーの生産量が大きく減少すると予想されている。
コーヒーの2050年問題と言われるものだ。
そのため、世界では今、地球環境に配慮した「代替コーヒー」が模索されている。
CO2を減らす製造方法を選んだり、コーヒー豆以外の材料を使ったりして、コーヒーに代わる飲料が続々と開発されている。
そう、玄米デカフェのような代替コーヒーは、「新たなサスティナビリティの選択肢」として急速に注目を集めているのだ。
ちなみに、改良を重ねた玄米デカフェは、飲みものとしての完成度も格段に上がり、10数種類の全国各地のお米を使ったラインナップを展開するに至っている。
そして、直近の2025年4月。
シンガポールの食品の展示会で、玄米デカフェを試飲したのは、シンガポールやマレーシア、タイ、ベトナムのディストリビューターたちだった。
彼らは期待を込めたまなざしを向け、口々に言った。
「“ジャパニーズ・ライスコーヒー”はとてもおいしいね」
「ナイスな飲みものだよ」「これは新しい味だね」———
そもそも世界の食文化やライフスタイルは、もう出来上がってしまっている。
そこに入り込むような新商品を作ることは、とてつもなく難しいのはわかっている。
しかしながら、玄米デカフェを試飲した、彼らの表情が教えてくれた。
代替コーヒーを模索する人の中で、玄米デカフェを受け入れてもらえる可能性がある。
玄米デカフェは未来の飲み物になり得る。
そう確信したのだ。
それがパズルのピースが組み合わさり、「絵」が浮かび上がった瞬間だった。
(*)庄内町新産業創造館「クラッセ」の中にある工房。クラッセは、2014年に「農・商・工・観」連携の6次産業化を促す拠点として開設された。そこでは町の人が地元の食材などを使った新商品の開発や製造に取り組んでいる。
玄米デカフェの新工場と農福連携
さて、その「絵」とは何か?
ここで私が描く玄米デカフェの未来図について話したい。
お伝えしたように、玄米デカフェには世界に打って出るチャンスが十分にあると考えている。
我々はすでに庄内町で10年以上玄米デカフェを作ってきた礎がある。
これを活かさない手はないと思っている。
まず現在、玄米デカフェの製造は、庄内の小さな1工房で行っている。
しかし、将来的にはもっと大きな工場にしたいと考えている。
そこは単なる、機械中心の製造工場ではない。
地域の人たちを中心に、引きこもり経験がある人などにも関わってもらえるような場にしたい。
工場には「カフェ」もある。
若年たちが焙煎する玄米デカフェや、お米から作られたスイーツなどを楽しめる場だ。
私はその工場を、現在調布にあるMNHのコミュニティ工場のように、MNHの理念が息づくシンボリックな場にしたいと思っている。
そしてもう一つ。
そこで「農業」をやりたいと思っている。
どういうことか?
ご存知の通り、お米の消費量は年々減少しており、今後も加速していくと考えられている(*1)。そこに米農家の高齢化が拍車をかけ、作付面積も減少。
そもそも重労働であるのに儲からないため、後継者もいなくなってきている。それにより休耕田が増え続けるという負の連鎖が起こっている。
現在の政権においても、米価格の高騰に対し、備蓄米の放出などの政策が次々と講じられている。だが、どれも小手先の策と思えてならない。
問題の本質に目を向けないと、根本的な解決にはならないからだ。
そんな背景の中で、我々は庄内で新しい農業の形を創っていきたいと考えている。
すなわち、玄米デカフェを軸にした「農福連携(*2)のモデル」だ。
現在、確かに農家の担い手は減っている。
だが、働き手が本当にいないかというと、そうではない。
例えば日本の中で、引きこもりの人は推計146万人(*3)。実際はその3倍いるといわれており、438万人も存在する。障がいを持った人はそれ以上いる。
そして彼らは働く場を求めている。
事実、MNHは創業依頼、彼らの手をお借りして、事業を行ってきている。
そこで、農業と福祉の両面の課題を解決することをめざし、新しい農業の形を作りたい。
具体的には、庄内町にある田んぼを借りて、工場で働く若者たちと一緒に稲作を始めたいと思っている。
すると、お米づくりから、加工して食品を作るところまで手掛けられることになる。
要は、かねてからの望みである「お米を守っていくこと」に、“一気通貫”で携われることになるのだ(*4)。
(*1)国民1人が1年間に食べているお米は、1962年の118.3kgをピークに減少し続け、2022年では50.7kgと約半分の消費量となっている。
(*2)農業と福祉が協力して障がい者などの就労や生きがいを創出する取り組み。
(*3)2022年11月に行った内閣府のアンケート調査より。
(*4)とれたお米をオリジナルの商品にして販売することもできると考えている。
新しい米の価値が生み出される場
今に話を戻そう。
2025年7月現在、新工場を建てる計画が、実際に進行している。
そこをゆくゆくは庄内における「新しいお米の価値を生み出す場」として、町のために集客を図りたいと思っている。
つまり、庄内町で観光業を行いたいと願っている。
もとより我々は、地域の活性化を目的にした事業にも力を入れてきた。
都会に若者がどんどん流れてしまう中で、自分の育った地域でやりがいを持って働く若者を増やすこと。それが日本全体を幸せにすることにつながると思うからだ(庄内での事業もその一環である)。
一方で、「そこに行かないとだめなもの」という観光業の特性も見逃せない。
地域の魅力をうまくブランディングし、他県から人を集めることは、地域経済にとって重要だと思うからだ。
とはいえ庄内は、観光地でもあるけど、観光客は少ない。
そんな地域にどうやって人を呼んだらよいのか?
ここに関しては、温めてきたアイデアがある。
例えば、友だちから「自分が案内するから田舎に一緒に行こう」と誘われれば、行く人もいると思っている。つまりその土地の「関係者」が、他県から人を呼んでくるのだ。
MNHは10年以上も前から庄内町で事業を行ってきた。
行政の方々をはじめ、町の方とも良好な人間関係を築いている。
彼らと協力していけば、例えば農業や田舎暮らしなどの、体験型のメニューを作ることも可能だ。
すなわち我々の資源を活用して、質の高い交流観光を生み出していけると想像している。
もっと言うと、シリコンバレーという片田舎の町が、IT産業の集積地として有名になったように、新しい飲みものの発祥地として庄内町が知れ渡り、交流人口をどんどん増やしていければ、この上なく嬉しい。
以上のように、ゆくゆくはMNHにしか手掛けられない観光を、手掛けていきたいと願っている(*)。
(*)余談だが近い将来、玄米デカフェを販売する小売店も東京に持ちたいと思っている。