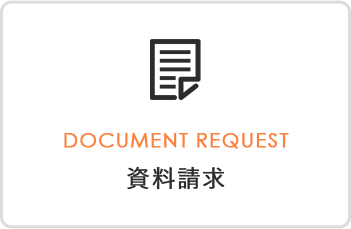ゲスト対談・特集記事
連載
庄内から世界に向けた商品を ~ 玄米デカフェのブランドマネージャー募集にあたって~
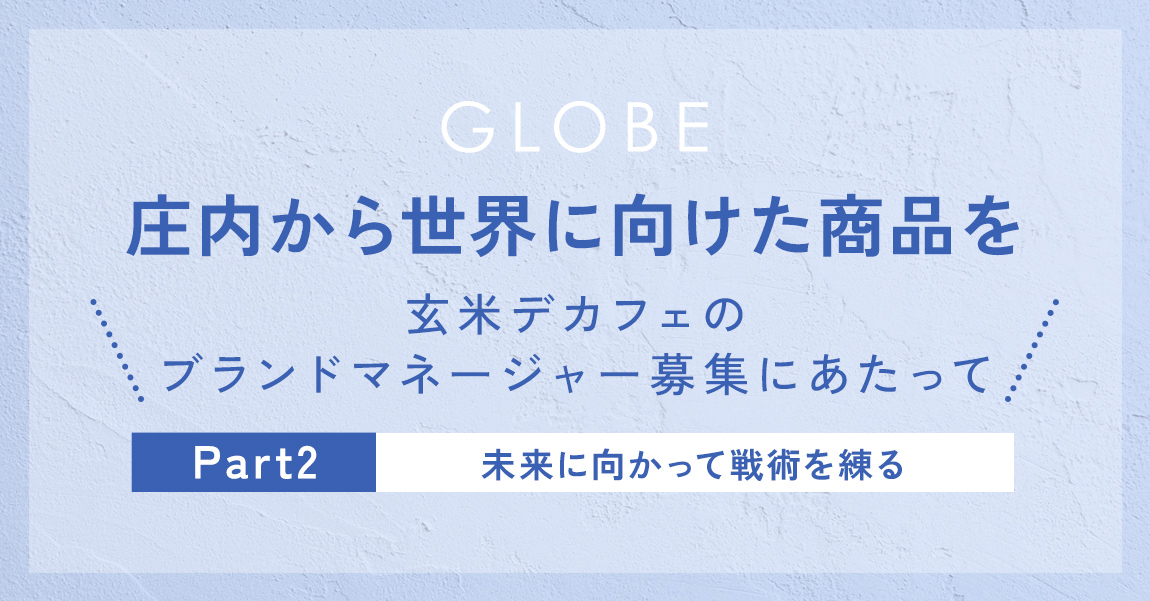
Part.2 未来に向かって戦術を練る
現在、玄米デカフェは、順調に需要が増えてきた。
国内の販路も増え、海外の商談も複数進めていている。
加えて現在、玄米デカフェの「エスプレッソ」ができ上がりつつある。
すると、成長がより加速すると思われる。
なぜか?
コーヒーを飲む場というのは、世界的に見ても、圧倒的に「カフェ」が多い。
そんなカフェに新しいコーヒーを提案する際、新しくドリップの機械を置いてもらうのはハードルが高い。
売れるかどうか分からないもののために、カフェ側もコストをかけられないからだ。
しかし、エスプレッソはというと、もともと1回ずつ淹れる飲み物だ。
それゆえに導入してもらいやすいのでは、と考えている(*)。
ちなみに私がこのエスプレッソを試飲してみた印象では、かなり美味しい。しかも普通のカフェラテより好きだと思えるし、何よりカフェインがない。これが夜でも飲めるのかと思うと嬉しくてたまらない。
だから需要も高まるであろうと予想している。
前置きが長くなったが、以上のような背景の中で、私と一緒に玄米デカフェというブランドのマネジメントを行ってくれる人材(ブランドマネージャー)を募集するに至った。
(*)既にあるエスプレッソマシンに、玄米デカフェ用の中身を入れてもらえばよいから。
MNHの考える「ブランドマネージャー」とは?
「ブランドマネージャー」とは、一般的に、マーケティングやブランディングで自社商品を効果的に打ち出していく仕事を指すだろう。
これを読まれている方や、よく勉強されている方の頭の中には、「市場調査」「ブランドコンセプトの策定」「プロモーション戦略」……そんな言葉があり、人によってはデータとにらめっこしたり、うんうんうなって企画したりするようなイメージも、あるのではなかろうか。
しかし、MNHのブランドマネージャーは、違う。
まず、玄米デカフェの企画だけを担当する仕事ではない。
これは当社の規模も関係はしているが、何より私自身、商品に関するすべてのことがその人の中で腑に落ちていないと、本来的な企画はできないと思っているからだ。
ここに関しては勘違いを防ぎたいため、例も挙げよう。
世の中の比較的大きめのメーカーには、製造と企画(開発)と営業の担当がいる。
彼らはたいがい、すれ違いを起こしやすいと言える。
製造の現場を知らない人が企画を担当すると、技術方法などの現場を無視した製品になりがちだ。
「アイデアはいいけど、一体どうやって作るの?」といった具合に。
かたや製造の現場をまったく知らない営業担当は、ときに無理な注文を受けてくる。
よくある「お客さんが言うんだから1週間でやってよ」的なパターンだ。
ようは実態を知らないと、結局は机上の空論に終わってしまうのだ。
仮に大企業において、成熟しきった商品を回すだけの仕事であれば、もしかしたらこのような分業はあり得るのかもしれない。しかし玄米デカフェは真逆だ。
これから世界に受け入れられるブランドを作っていく仕事なのである。にらめっこする過去のデータなどは、どこにもない。
日本のコメ事情はもとより、製品の製造方法も熟知していなければならない。
どんなお客さんが興味を持っていて、誰が買ってくれているのかも知らないといけない。
さらに世界でどんな需要があり、どんな立場の人が、どんなタイミングで飲んでくれそうなのか。
そのターゲットごとにどうやって営業し、どんなふうに販売すれば良いのか———
ブランドマネージャーは、そのように製造・企画・営業・販売など、あらゆる方面から商品の未来を考えなくてはならない。
ちなみに、現状こういったことをすべて把握しているのは、当社においては社長である私しかいない。その仕事を、今後拡大期に入るにあたって、一緒になってやってくれる人材を必要としている。
今、一番推し進めたい商品のブランドマネージャーであるため、いわば当社における「玄米デカフェの社長」といっても過言ではない。
一方でこの仕事を、会社の指揮系統の観点から言い換えてみる。
まず、MNHにおいて商品を打ち出していくことは、
「未来に向かって戦略を共有し、戦術を作り、戦闘をする」ことだ。
戦闘をするのは、営業部隊と製造のスタッフだ。
戦略は、社長である私が考える。
ブランドマネージャーは、その戦略を理解して、私と一緒に戦術を練る人だ。
戦術とは、繰り返すが、世の中の需要を鑑みた上で、どういう商品があった方がいいのか。
それを作るためにはどういう製造背景が必要か。
どのようなところに営業をかけたら、効果的にその商品が広がっていくのか。
それらを考えるのが、ブランドマネージャーの一番の仕事になる。
重要なのは現場を知ること
ブランドマネージャーが戦術を練るためには、「現場を知ること」がとても重要だ。
その理由は1つ。本当の答えは現場にしか存在しないからだ。
商品が売れる現場にいて初めて、その商品がお金に変わる瞬間を感じ取れる。
どういうお客さんが、どんな表情で買っていくのか。
そこを理解しないと売れるものは生まれない。
最も良くないのは、販売の現場にいかず、頭でっかちになってしまうこと。
つまり自分の思い込みや「こんなお客さんがこうやって買ってるらしい」と伝聞だけで判断することだ。
玄米デカフェは現在、主に百貨店などでポップアップ店舗を出し、販売をしている。
よって、そこで実際に売ってみることが必要になる。
そもそも戦術はずっと同じではなく、変わり得る。
これがいいだろうという戦術を立て、実際にやってみたらうまくいくこともあるだろう。逆にちょっと違ったというのも大いにある。
さらに戦術の可否は0か1でもなく、グラデーション的だ。
変更する部分もあるけど、そのままいく部分ある。今だったらいけそうなので、瞬間的に加速させる、という判断もあるだろう。
そのようにPDCAを繰り返していくのだが、それを回すのには、現場を見ることが絶対的に必要なのだ。
一方で、現場のオペレーションをきちんと回すためにも、現場を知ることは重要だ。
例えばオフィスで「こういう順番で並べていれば、お客さんがわかりやすいだろう」と企画する。
だが、実際の現場では、そのようにならないことの方が多い。
お客さんがその順番で見てくれないかもしれないし、ぐちゃぐちゃにしてしまうかもしれない。
つまり、「実態にそったオペレーション」は、現場を見ないと生み出されないのだ。
もう一つ、データを過信しない、というのも私のポリシーだ。
例えばコンビニエンスストア業界では、データマーケティングが主流だ。
この時期・この時間帯に、この年代層にこれが売れるというデータが蓄積されていて、それをもとに品揃えを変えている。
確かに売れるのだろうが、データだけでやっていくと、商品がつまらなくなる可能性もあると思っている。
コンビニはその性質上、仕方がないと思うが、仮に売れるものだけが並んでいるお店があったとする。でもお店としての魅力は、そこにあるのだろうか?
多様な商品があるからこそ、売れるものも出てくる。
みんなが欲しいマス商品だけではなく、ニッチな商品もあるから、選ぶのが楽しい。
そんなふうに私は感じている。
現場でものを売るのは大変ではある。
ただし、現場の雰囲気を感じながら売ってみることは、見えなかった需要にも気づくこともあるし、何より自分で作った商品が売れるという感動が味わえる。
だからこそ、ものづくりは楽しいのだ、と私は思っている。